栄養学のキホン
糖質とは?エネルギー代謝の中心にある栄養素
糖質は三大栄養素のひとつであり、ATP(アデノシン三リン酸)を生合成する主要な材料です。ATPは筋収縮や神経伝達など、生命活動のあらゆる場面で使われるエネルギー分子であり、糖質と脂質から最も効率よく生合成されます。
炭水化物・糖質・食物繊維の関係炭水化物・糖質・食物繊維の関係
「炭水化物=糖質」と思われがちですが、実際には以下のように分類されます:
- 炭水化物:糖質+食物繊維
- 糖質:単糖類~多糖類までの消化・吸収される成分
- 食物繊維:消化されず腸内環境に働きかける成分
糖質の分類と代表例
糖質は構造によって以下のように分類されます
| 分類 | 主な種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| 単糖類 | グルコース、フルクトース、ガラクトース | 最も基本的な糖質単位。直接吸収される |
| 二糖類 | スクロース、ラクトース、マルトース | 単糖が2つ結合。消化吸収が早い |
| オリゴ糖 | フラクトオリゴ糖など | 数個の単糖が結合。腸内環境に影響 |
| 多糖類 | でんぷん、グリコーゲン | 多数の単糖が連なり、エネルギー源として重要 |
グルコースの役割と代謝経路
グルコース(ブドウ糖)は、血糖値として管理される最も重要な糖質です。筋肉や肝臓にグリコーゲンとして貯蔵され、必要に応じてエネルギーとして利用されます。
- グリコーゲンが枯渇すると「糖新生」によって補われる
- 過剰なグルコースは脂肪として蓄積される
- グルコースは解糖系 → TCA回路 → 電子伝達系を経てATPを生成
フルクトースとガラクトースの特徴
- フルクトース(果糖):単糖類の中で最も甘く、果物やはちみつに多く含まれる。小腸から吸収され、肝臓でグルコースに変換される。
- ガラクトース:乳糖(ラクトース)の構成成分。体内でグルコースに変換される。
食物繊維の分類と働き
食物繊維は構造的には多糖類ですが、人の消化酵素では分解できません。腸内細菌によって分解され、短鎖脂肪酸となり一部が吸収されます。
| 分類 | 主な種類 | 働き |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | ペクチン、アルギン酸、グルコマンナン、β-グルカン | 血糖値の急上昇抑制、腸内環境改善 |
| 不溶性食物繊維 | セルロース、ヘミセルロース(大豆、ごぼうなど) | 便通改善、コレステロール吸収抑制 |
糖質の代謝と多様な役割
糖質はエネルギー源としてだけでなく、以下のような多様な生理機能にも関与します
- エネルギー貯蔵:グリコーゲンとして筋肉や肝臓に蓄積
- 脂肪合成:過剰な糖質は中性脂肪に変換
- アミノ酸・たんぱく質合成:糖質由来の炭素骨格が利用される
- 糖タンパク質・糖脂質の構成:細胞膜や免疫機能に関与
- 核酸合成:リボース-5-リン酸がDNA/RNAの材料に
- 解毒物質供給:UDP-グルクロン酸による抱合反応
- 血糖維持:糖新生やグリコーゲン分解による調整
まとめ
糖質は単なる「甘いもの」ではなく、生命活動の根幹を支える栄養素です。種類や代謝経路、役割を理解することで、スポーツ栄養や健康管理においてより効果的な食事設計が可能になります。
カロリー自動計算ツール



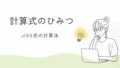
コメント